 友人と手書きのメモを送受信することが多くなってきたので、タブレットか何かが欲しくなってきた。しかし、タブレットは使い慣れないと、ものすごく難儀するので、手軽に利用できるスキャナを導入することに決めた。 友人と手書きのメモを送受信することが多くなってきたので、タブレットか何かが欲しくなってきた。しかし、タブレットは使い慣れないと、ものすごく難儀するので、手軽に利用できるスキャナを導入することに決めた。
我が家は、父親の事務所にもコンピュータがあって、家族がワープロやデザイン用の事務に利用していて、スキャナも実はあるのだが、何かと不自由だし、なんと言ってもLAN接続していないので、こちらにもスキャナを導入することにした。 購入したスキャナは、かなり安いものしか買えなかったのだが、Mustek(富士通販売)の1200CUだ。『フラットヘッド、USB接続、600dpi以上、光源の種類はこの際構わない』で1万円台前半でコレに決定。 他にもCanonのものも対抗馬になったわけだが、縦方向の光学解像度が1200dpiというのにつられてコレになった・・・。(笑)
 最近のスキャナは、何しろ薄くなった。この薄さは、意外と使い勝手に貢献する。どこにおいても目立たない(邪魔にならない)のだ。今回は、コンピュータの上に置いて使うことにした。 最近のスキャナは、何しろ薄くなった。この薄さは、意外と使い勝手に貢献する。どこにおいても目立たない(邪魔にならない)のだ。今回は、コンピュータの上に置いて使うことにした。
このスキャナはCIS光源を採用していて、光源の色の3原色を瞬間的に,、かつ順番に切り替えていき、受光部を1種類のみにすることによってコストダウンを図ったタイプだ。瞬間的には赤・緑・青のいずれかしか発光していないため、1ライン毎に3回の光源が順次点灯する仕組みになっているわけだ。この方式は、厚みのあるものをスキャンすると、虹色のボケが出てしまうという欠点があるが、安価である。 ちなみにこれよりも高級なスキャナ(一般的なスキャナ)は、白色光源を採用し、3種類の受光部を用意している。 このスキャナは、低解像度でスキャンすると、ほんの少しではあるが、虹色のボケが出てしまった。順次点灯する光源の周期と、ヘッドを移動・停止させるサーボとが、しっかり同期が出来ていないようだ。低解像度だとヘッドが高速で移動するため、ヘッドの質量の慣性の法則によって、サーボがきちんと止めたり加速することが出来ていない事が原因と思われる。サーボのトルクが足りないのか・・・。ベルトがゆるいのか・・・。もしくは、サーボなどではなく、単なるモータを使っているのか?!(モータは、「瞬時に停止させる」という機能がない。つまり動きっぱなしで速度調節のみ。もちろん安価だ。) しかし、ヘッドが低速で移動する最高画質(600〜1200dpi)設定にすれば、光源の虹色が画像に現れる現象からも解放されるようだ。殆ど気にならないレベルまで抑えこまれている。 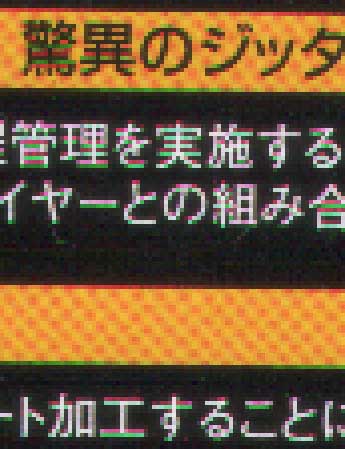 | 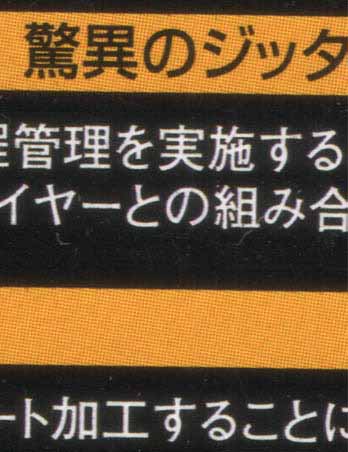 | ▲150dpiを3倍に拡大
横線に虹色のボケが見える。
また、印刷のハーフトーンの模様の
干渉模様が見えてしまっている。 | ▲1200dpiを1/2に縮小 | というわけで、虹色が気になるような場合には、最高画質でスキャンして、その後画像編集ソフトで、希望の解像度に変換するという作業が発生する。この場合には、最高画質の遅いスキャニングを強いられるわけだが、USB転送もそれほど遅くないし、どちらにしろ、スキャンしっぱなしで編集作業が無いことは無いわけで、使い勝手の上で、コレと言った不自由はないのだ。 この点を考慮しながら使えば、なかなか良いスキャナだ。最高画質の『画質』は想像以上のレベルだった。 |